
篳篥
ひちりき

篳篥は漆(うるし)を塗った竹の管で作られる。
音を出す部分はオーボエやファゴットと同じように葦(あし)を削ったリードが使われており、取り外し交換できるようになっている。
ただし、篳篥のリードは2枚を重ねているのではなく葦を平らにつぶしてある。
小さな文字では見にくいでしょうから、大きな文字にしました
篳篥[ひちりき]
または
觱篥
[ひつりつ]
中国・朝鮮から日本に伝来した頃には、觱篥(ひつりつ)という言い回しがあったようだ。
|
古くは大篳篥と小篳篥があり、大篳篥は鎌倉時代(1200年ごろ)にはすでにすたれており使われなくなっていたようだ。現在使われている篳篥は小篳篥で、単に篳篥といえば小篳篥のこと。
信西古楽図の篳篥
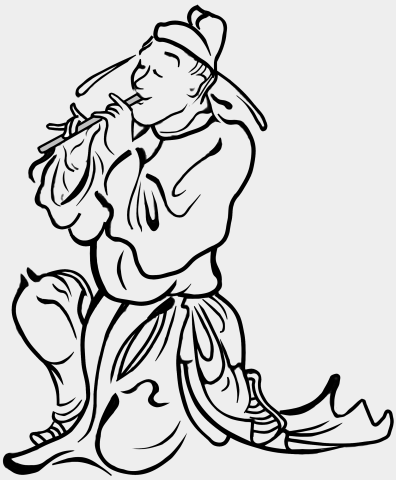
信西古楽図は、唐代 宮廷の宴饗楽を墨画で描いたもの。篳篥を奏でる楽人が描かれているが、この篳篥は大篳篥だと思われる。
|
雅楽では、
笙(しょう)
、
篳篥(ひちりき)
、
龍笛(りゅうてき)
を三管と呼ぶ。

私家版 楽器事典
/
楽器図鑑
gakki jiten
|
| |
