
胡弓
こきゅう
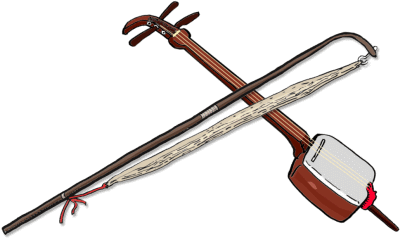
中国の二胡(にこ)と混同されることがあるが、胡弓は日本の楽器で江戸初期ごろから使われたようだ。三味線が原型のようである。このイラストは3弦だが4弦の胡弓もある。
糸(弦)を選ぶのは弓で角度をつけるのではなく、胡弓本体をクルリと回して擦る糸を選択する。 これは胡弓に限ったことではなく、弓奏楽器は本体を回転させる方法をとるものが多い。 弓は鉛筆を持つような格好で、毛の張りを調節しながら弾く。 広義で「胡弓」は弦をこすって音を出す擦弦楽器(さつげんががっき )の総称として呼ばれることがあり、沖縄にはクーチョーという擦弦楽器があるが、これも漢字では胡弓と書く。
 クーチョー
|
豪絃(ごうげん)
クーチョー
|
豪絃(ごうげん)
 二胡
|
墜琴(ツイチン)
二胡
|
墜琴(ツイチン)
gakki jiten |