パン フルート
Panflute
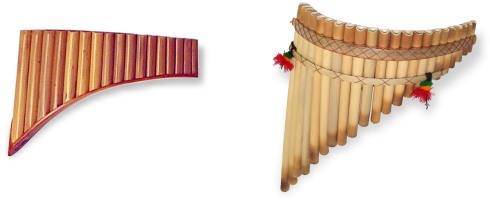 パン【Pan】
パン【Pan】
ギリシア神話で、牧人と家畜の神。あご髪(ひげ)をたくわえ、山羊の角と脚を持った半獣神。
山野を走り回り、好んで笛を吹いたという。
ローマ神話のファウヌスにあたる。
(大辞泉より引用)
というわけで、パンフルート名前の由来は、この「牧人と家畜の神」からつけられたそうだ。
管に息を吹き込んで音を鳴らす。息が漏れる音と、管で響く音とが絶妙に調和して癒し系の音色が発生する。
息を吹き込むといえば、学校の理科の時間。何かの化学実験の時間に、試験管を並べて吹いたことはないだろうか。そう・・・ないですか。それは残念。
南米のサンポーニャは今も民族楽器として存在するが、パンフルートは今や一般化した大衆楽器だ。
パンフルートとサンポーニャは起源が違うのだろうけど、
サンポーニャもひっくるめてこのような形態をした楽器を総じてパンフルート(またはパンパイプ)と呼ぶようになった。ルーマニアでは「ナイ(Nai)」、
中国・日本では漢字で「排簫(はいしょう)」と書く。

 サンポーニャ
|
排簫(はいしょう)
|
アンターラ
サンポーニャ
|
排簫(はいしょう)
|
アンターラ
 ヴォット
|
ナイ
ヴォット
|
ナイ
私家版楽器事典
/
楽器図鑑
IROM BOOK GAKKI JITEN
| 
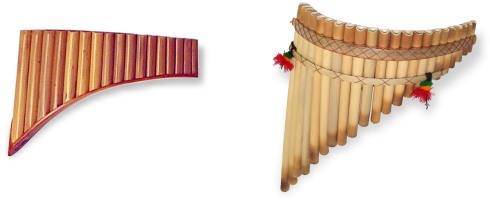
 サンポーニャ
|
排簫(はいしょう)
|
アンターラ
サンポーニャ
|
排簫(はいしょう)
|
アンターラ
 ヴォット
|
ナイ
ヴォット
|
ナイ
