
ラケット/ランケット
Rackett / Rankett
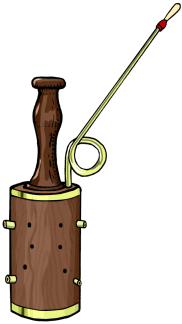
木管楽器というべきだろうが、何と言うか、不思議な形をしている。私が子供の頃、稲の縄を結う時に隣のおじいさんがこんな形をした道具で稲を叩いていたなあ、確か。 重症の肩こりの時に使う肩たたきにいいかもしれないし、一輪挿しの花瓶のようで、また、しゃれたトックリのようでもあるけれど中身の構造は蓮根だ。 穴が10本、蓮根の通気孔のように通っていて出口までつながってる。穴はぐるぐると長いので見た目より低い音がでる。 日本ではラケットと表記することが多いけど、テニスのラケットと間違わないようにランケットのほうがいいのにね。 ファゴットやオーボエと同じ2枚リードの楽器。 上のイラストは、バロック型のラケットでリードと本体の間に細い管(クルーク)が付いているが、 リードが本体に直接付いているルネサンス型のラケットもある。
 ファゴット
|
オーボエ
ファゴット
|
オーボエ
IROMBOOK |
