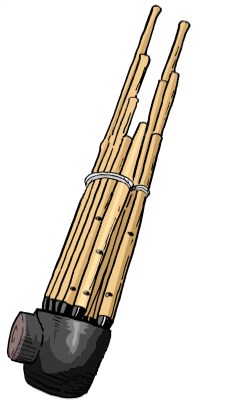

|
日本の伝統楽器。
雅楽で使われる。
リード(笙では『した』とよぶ)を振動させて音を出す。ふいてもすっても同じ音が出るので息継ぎの途切れがなく連続して音を出すことができるのが特徴
(この発想というか仕組みはアコーディオンと似ているかもしれない)。
管には、穴が開いており、これを塞いだり放したりすることで何種類かの和音が出る。
和式の結婚式では笙の音がバックグラウンドミュージックとして流れるのはおなじみだ。
笙は、翼を立てて休んでいる鳳凰(ほうおう)に見立てられ、鳳笙(ほうしょう)とも呼ばれる。
雅楽では、
笙(しょう)
、
篳篥(ひちりき)
、
龍笛(りゅうてき)
を三管と呼ぶ。
笙は中国のシェンが日本に伝わったもの。シェンはアコーディオンやハーモニカなどに影響を与えたフリーリード楽器の元祖だ。
とはいえ、中国のシェンが最古の笙であるかというとそうではないようだ。中国よりもっと南、東南アジアでこの楽器のアイデアがうまれたのではないかと思われる。
 笙の仲間 あれこれ
笙の仲間 あれこれ
 フリーリードの楽器
フリーリードの楽器
|
|

