
|
三線 さんしん 三線はヘビの皮を胴に張っている。 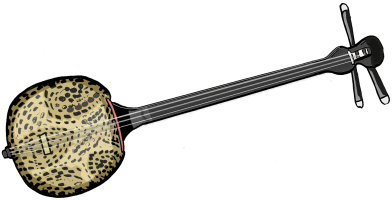
三味線 しゃみせん 三味線はネコやイヌの皮を胴に張っている。 
チャランゴ charango チャランゴはアルマジロの胴体を共鳴箱に使うことがある。 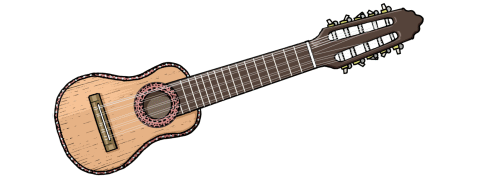
キハーダ quijada キハーダはウマやロバのアゴの骨を乾燥させて作る。 
ダマル Damaru 人骨だ。どこの骨だかよく見れば判る。 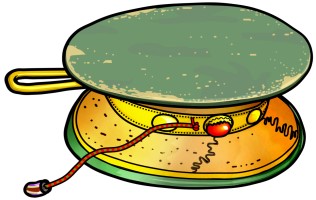
カンリン Rkang gling これも人骨だ。大腿骨。 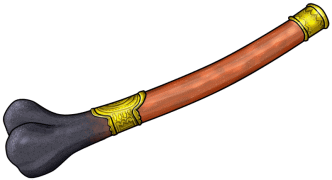
バイオリンの弓 Violin bow バイオリンの弓はウマのシッポの毛。 
太鼓 たいこ/Drum 動物(獣)の皮をはった太鼓。 

ツノの笛/象牙のラッパ Bugle / Ivory horn 牛の角(つの)や象牙で作った管楽器。hornは、つまりホルンだ。 

爪のラットル Hoof rattle ヤギの爪で作ったラットル(ガラガラ)。 
リラ Lyre / Leier / Lira 世界のいたるところでこの形の弦楽器は作られ、様々な材料が使われる。 これは亀の甲羅を使ったリラ。 
ザンポーニャ Zampogna 羊をまるごと 
私家版 楽器事典 / 楽器図鑑 |