 ウード ウード
 テオルボ テオルボ
 ピパ(中国の琵琶) ピパ(中国の琵琶)
 リュート リュート
|

琵琶
びわ

楽琵琶
がくびわ
楽琵琶は雅楽で用いる琵琶。日本の琵琶の中で最も大きい。棹(ネック)が細く、低い柱(フレット)が付いているのが特徴。合奏の中では分散和音を演奏する。

平家琵琶
へいけびわ
楽琵琶と同じ系列の琵琶だが楽琵琶より少し小さい。平家物語を琵琶の伴奏で語る「平曲」で使う琵琶。
盲僧琵琶
もうそうびわ
奈良時代より現れた琵琶。盲人の僧侶がこの琵琶の伴奏で経文を唱えた。
全体が細身なので笹琵琶とも呼ばれたようだ。娯楽的な楽曲にも使用された。
|

|
薩摩琵琶
さつまびわ
武士の士気を鼓舞するため、盲僧琵琶を改造したのが始まりという。
大きな撥(ばち)で叩き付ける打楽器的奏法を可能した。
荒々しい楽曲で武士のモチベーションを高めたのだろう。
|

|
筑前琵琶
ちくぜんびわ
筑前琵琶は、薩摩琵琶に対抗して作られた比較的新しい琵琶。
明治になってから福岡で優雅な新曲も登場し広まり、女性に人気があったという。
膝の上に縦に構えて、大きめの撥(ばち)ではじく。
|

|
錦琵琶
にしきびわ
大正時代、永田錦心(ながたきんしん)の思想を受け継ぎ、水藤錦穣(すいとうきんじょう)などにより作られた琵琶。
5弦5柱であり、弦の一組は復弦になっている。
膝の上に縦に構えて、とても大きな撥(ばち)ではじく。
(右のイラストは 錦琵琶の宗家であり美人奏者の水藤錦穣。昭和初期の写真をもとにイラストに転写させていただいた)
|

|
信西古楽図 (しんぜいこがくず)の琵琶

信西古楽図は、唐代 宮廷の宴饗楽を墨画で描いたもの。琵琶の他にもたくさんの楽器奏者が描かれている。
雲中供養菩薩像 (うんちゅうくようぼさつぞう)

平等院の鳳凰堂には雲中供養菩薩像と呼ばれる52体の菩薩像が掛けられている。
上記の琵琶だけではなく たくさんの楽器を演奏している姿が表現されている。
藤原師長 (ふじわらのもろなが)
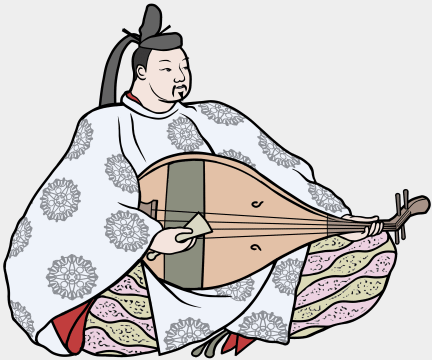
藤原師長は、平安時代末期の公卿(最高幹部として国政を担う職位)。
平安時代を代表する雅楽の音楽家で特に箏や琵琶の名手として知られており、当時のあらゆる音楽分野に精通していたといわれている。
箏について「仁智要録(じんちようろく)」、琵琶について「三五要録(さんごようろく)」などを書き表している。
|
|
琵琶の祖先
琵琶の祖先は、西アジアの弦楽器。
東へ東へ伝わり、日本へは中国から伝来した。
中国日本の琵琶も、西洋のリュートも、古代ペルシアのバルバットという楽器がルーツだといわれている。
|
私家版 楽器事典 / 楽器図鑑
gakki jiten
|
|