|
 西洋の音楽様式 西洋の音楽様式

 角笛が金管楽器に
角笛が金管楽器に
 弦を擦ったのは だれ
弦を擦ったのは だれ
 バルバット東へ西へ
バルバット東へ西へ
 サントゥール東へ西へ
サントゥール東へ西へ
 ブラギーニャ
ブラギーニャ
|
|
弦をこすったのは だれ

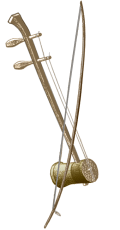
|
ラヴァナストロン(世界楽器大事典より引用)
弓奏楽器の起源説に「ラヴァナストロン説」というのがある。
これは五千年前に、セイロンのラヴァナ王が発明したというもの。
この話がはじめて知らされたのは、多分フランス人のソネラート(sonnerat)という人の旅行記『東インドとシナの旅』の中に、円形胴の楽器を発表し、これがヨーロッパに伝わって、この説が評判になったものである。
しかし、第一にラヴァナ王の歴史的存在が怪しいものであり、それに著者がラヴァナストロンとしてあげた図は、ほんとうのインドでいうラヴァナストロンでなかったりして、この節は単なる俗説となってしまった。
|
このラヴァナス王というのは、有名なインドの歌劇『ラーマーヤナ』の悪役で、ラーマー王子の妃シータ姫をかどわかして、大戦争のすえラーマ王子は猿王ハヌマンの援軍をえて、シータ姫を奪い返したという長編の詞劇で知られている。
これは昔、西北部からインドに移住したアーリア人が原住民を南部に圧迫した歴史を背景にしたもので、ラヴァナ王は夜叉王となっており、その配下は阿修羅とされている。
この話からみても、弓奏楽器の起源がラヴァナ王だというインド人の考えを裏返しにすると、この楽器はアーリア人が持って来たものではなく、古くからインド原住民が持っていたことになる。
それを裏づけるように、インドには弓奏楽器の種類が多種多様で、たいへん多い。
しかし、インドの権威ある中世までの楽書には、この種の楽器名がなかったことを考える必要があろう。
ラヴァナストロン、またはラヴァナストラは竹筒を胴とした、いわゆるシナ胡弓であり、
腕で抱えて弾くものにサーランギ、サリンダがあり、また高度い改良されたバラサラスバティまたはタウスと呼ばれるヴィーナを弓奏するような進歩したものもある。
|
| |



