
|
オルゴール 3個〜6個ほどの鉦(かね)を L字形の木製台に取り付けてある。下座音楽では、蝶の飛ぶ場面や虫の音に用いられる。 
駅路 うまやじ/えきろ 宿場・街道の場面の囃子(はやし)で用いる。馬に乗って旅する場面とかだね。 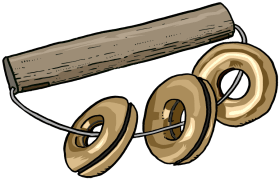
チャッパ 手平金(てびらがね)、銅拍子(どうびょうし)ということもあるが、下座ではチャッパと呼ばれている。 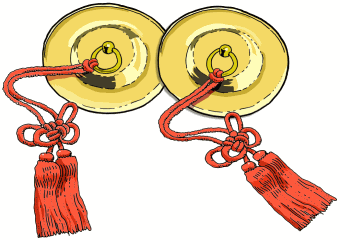
時計 とけい 歯車でカリカリ、コチコチと鳴るパーカッション。いわゆるラチェットだけど、下座音楽では「時計」呼ぶようだ。 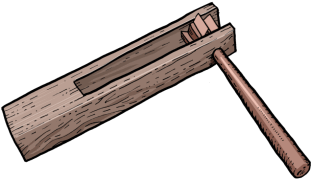
雨団扇 あめうちわ 雨の擬音を出す。うちわにビーズなんかを糸でくっつけてある。 
四つ竹 よつだけ 太い竹で出来ている。ちょっとビンボーな長屋の場面で使われる。 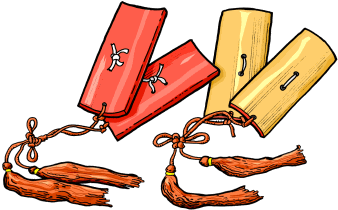
大拍子 だいびょうし 胴の長い締太鼓。細い桴(ばち)でたたく。 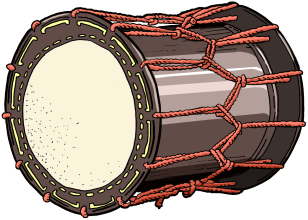
締太鼓 しめだいこ 古い伝統的な呼び名は猿楽太鼓(さるがくだいこ)。 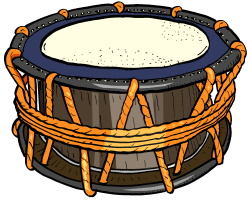
篠笛 しのぶえ 祭囃子(まつりばやし)でも使う庶民の横笛。 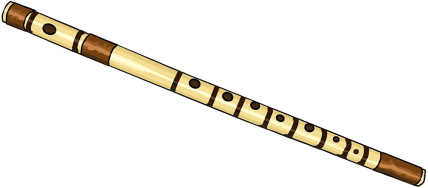
能管 のうかん 笛の内部に特別な仕掛けがしてあり、音程はあまりハッキリしていないので効果音として使うことが多い。幽霊が出てくる時、「ヒュィ〜」と鳴っているのがこの能管。 
三味線 しゃみせん 三味線は「太棹」「中棹」「細棹」に大別される。歌舞伎では長唄の伴奏で、主に「細棹」が使われているようだ。 
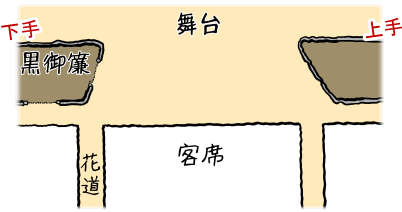
私家版 鳴り物事典 / 鳴り物図鑑 |

