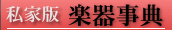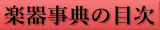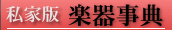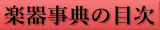コトドリ(琴鳥)
タテゴトアザラシ
ガラガラヘビ
 カネタタキ カネタタキ
スズムシ(鈴虫)
タイコウチ(太鼓打ち)
バイオリンムシ
マツムシ(松虫)
ギターフィッシュ
シャミセンガイ
シュモクザメ(撞木鮫)
スルメイカ
ピパ ピパ
ホラガイ(法螺貝)
コトクラゲ
ツリガネクラゲ
ツリガネムシ(釣鐘虫)
ラッパウニ(喇叭雲丹)
ラッパムシ(喇叭虫)
チャルメル草
ツリガネソウ(釣鐘草)
ペンペン草
ラッパスイセン(喇叭水仙)
|
カネタタキ(鉦叩き)
Kanetataki

 バッタ目カネタタキ科の昆虫。鳴き声が鉦(かね)をたたいているように聴こえる。
バッタ目カネタタキ科の昆虫。鳴き声が鉦(かね)をたたいているように聴こえる。
【鉦叩き】
[学名:Ornebius kanetataki]
昆虫綱直翅(ちょくし)目カネタタキ科に属する昆虫。コオロギの一種で、秋の鳴く虫の一つ。
体長10ミリメートル内外の小形で扁平(へんぺい)な虫。頭胸部は赤褐色、腹部は黒褐色であるが、全身を灰褐色の鱗片(りんぺん)が覆うので淡褐色にみえる。
雄の前翅は茶褐色である。頭部は小さく、それに続く前胸背部は後方に広がる台形状。雄だけが短い前翅をもち、後翅を欠く。雌は無翅。肢(あし)は全体に短い。
腹端には長い尾角をもち、雌では短い産卵管が突出する。成虫は8〜11月にみられ、生け垣や小低木上にすむ。
雄ははねをこすってチン、チン、チンと澄んだ音を出すが、この音が小さい鉦(かね)をたたいているように聞こえるのでカネタタキの名が出た。
関東地方以西に分布し、中国大陸にも生息する。
 Yahoo!百科事典より引用
:
2012年 当時の文面を記載させていただいております。
Yahoo!百科事典より引用
:
2012年 当時の文面を記載させていただいております。
|